
市販されている痔の薬は、以下の3つのタイプに分類できます。
- 軟膏タイプ
- 坐薬タイプ
- 内服薬(漢方)タイプ
※軟膏タイプの中には注入軟膏というものあり、症状によって使い分けが可能です。
軟膏・坐薬におけるステロイドの仕様・不使用に関してはメーカーによって扱いが異なりますし、意外と知られていませんが内服薬である漢方の中には痔に効くものも存在します。
今回は、そういった点を整理してみました。
ぜひ、ご自身の症状に合った痔の薬を見つけてくださいね。
1.軟膏タイプの痔の薬の効果
1-1.ボラギノールA軟膏とボラギノールM軟膏の特徴や違い
1-2.ステロイドが配合されていないボラギノールMシリーズ
1-3.プリザS軟膏とプリザエース軟膏の特徴や違い
2.座薬タイプの痔の薬の効果
2-1.ボラギノールAとボラギノールMの座薬の特徴や違いについて
2-2.プリザSとプリザエースの座薬の特徴や違い
2-3.注入軟膏と座薬の違いは?
3.軟膏・座薬タイプでステロイド配合のものは副作用に注意!
3-1.痔の市販薬はあくまで症状を抑えるもので、長期常用するものではない
3-2.副作用が心配なのは長期使用をした場合
4.痔に漢方が効く?内服薬の効果は?
4-1.乙字湯が痔に効く理由とメリット
4-2.乙字湯のデメリット
軟膏タイプの痔の薬の効果
軟膏タイプの痔の薬には、大別してチューブ式のスタンダードな軟膏と注入軟膏があります。
外痔核(いぼ痔)や裂肛(きれ痔)など、肛門の外側や肛門付近の幹部に使用するのに適しています。
内痔核(いぼ痔)や外痔核(いぼ痔)、裂肛(切れ痔)など、肛門の内側と外側の両方に使いたい方に最適です。
ボラギノールA軟膏とボラギノールM軟膏の特徴や違い
ボラギノールのシリーズはテレビCMなどもオンエアされているので、多くの方が知っている痔のお薬ですよね。
ボラギノールは軟膏タイプと坐薬タイプの2タイプを揃えていて、さらに軟膏タイプの中にも
- ボラギノールA軟膏
- ボラギノールA注入軟膏
といった感じで商品を揃えているので、症状に応じて使い分けることが可能です。
ボラギノールA軟膏とボラギノールA注入軟膏の使い分け
- 肛門の外側だけに使いたい方はボラギノールA軟膏
- 内痔核にも使いたい方にはボラギノールA注入軟膏
といった使い分けが最適です。
配合されている成分
どちらにもプレドニゾロン酢酸エステルと言われるステロイドが含まれているため、痛みや痒みの症状にも効果を発揮しますし、出血や腫れがある場合にも、効果が期待できます。
プレドニゾロン酢酸エステルは、一番ランクが低いⅤ.弱い(Weak)に分類されるため、全身への副作用はありません。
他にも痛みやかゆみを鎮めるリドカインや、傷の治りを助けるアラントインが含まれます。さらにビタミンE酢酸エステル(トコフェロール酢酸エステル)は、末梢の血液循環を改善するので、うっ血の改善に効果が期待できます。
楽天⇒ボラギノールA軟膏を確認
ステロイドが配合されていないボラギノールMシリーズ
武田薬品工業の同じシリーズのボラギノールMにも、軟膏タイプと座薬タイプがあります。
ボラギノールAとの大きな違いは、ステロイドが配合されていないという点です。
ですので痔の症状が軽度であったり、ステロイドを避けたい場合にはMシリーズを選びましょう。
配合成分は、局所の痛みやかゆみを鎮めるリドカインや、炎症を和らげてくれるグリチルレチン酸など。Aにも配合されている、アラントインやビタミンE酢酸エステル(トコフェロール酢酸エステル)も配合されています。
楽天⇒ボラギノールM軟膏を確認
プリザS軟膏とプリザエース軟膏の特徴や違い
こちらもテレビCMで有名な痔のお薬で、外側に使う軟膏タイプと内核痔(いぼ痔)に効果が期待できる注入軟膏タイプの両方が売られています。(注入軟膏は、プリザエースのみ)
Sとエースの違いを以下にまとめておきますね。
ステロイド濃度の違い
まず、どちらもヒドロコルチゾン酢酸エステルというステロイド剤が入っていますが、濃度に違いがあり、
- プリザSは100g中0.3g
- プリザエースは100g中0.5g
です。
麻酔成分濃度の違い
痛みやかゆみを抑える麻酔成分は、どちらも歯科医で局所麻酔などに使われている成分が使われています。
血管強化成分の配合量は、
- プリザSは1g
- プリザエースは3g
という差があります。
感染予防成分の配合量は、
- プリザSは0.2g
- プリザエースは0.25g
という差があります。
症状の重さで使い分ける
腫れや痛みや痒み、出血量が多い場合には有効成分が多いプリザエースがおススメで、症状がやや軽い場合にはストロイドなどの成分が低いプリザSで充分だと思います。
ボラギノールの場合は、AとMでステロイドの有無がはっきり分かれていましたが、プリザシリーズはステロイドの量の多さは違いますが、どちらにも含まれていますので、絶対にステロイドは嫌だ!という場合はボラギノールのMシリーズを選びましょう。
楽天⇒プリザS軟膏を確認
楽天⇒プリザエース軟膏を確認
基本的に、市販の軟膏タイプは特に症状がつらい時に使用するものです。
年中常用してしまうと、副作用が出る可能性もありますので、いつまでも治らない場合には、病院に行くのがベストです。
座薬タイプの痔の薬の効果
座薬タイプの市販の痔のお薬は、
- 内核痔(いぼ痔)
- 外痔核(いぼ痔)
- 裂肛(きれ痔)
の痛みや、かゆみの緩和に効果が期待できます。特に、肛門の内側で起こっている内核痔(いぼ痔)の痛みやかゆみでお悩みの方におススメのタイプです。
ボラギノールAとボラギノールMの座薬の特徴や違いについて
ボラギノールシリーズの座薬タイプは体温ですぐに溶けて拡がるように設計されていますので、痛みやかゆみの症状で困っている際に使えます。
(※ただし、それでもいぼ痔やきれ痔の場合は注入時に多少の痛みを伴う可能性が高いです。なるべく痛みを避けたい場合は、注入軟膏の方がおすすめです。成分は同じなので。)
軟膏と同様にAはステロイド配合で、Mはステロイド非配合と、大きな違いがあります。
Aはプレドニゾロン酢酸エステルと言われるステロイドが含まれているため、特に痛みや痒みなどの症状が強い状況での使用が望ましいです。軟膏タイプにも含まれている成分ですが、ステロイドの中では弱い方ですので、全身への副作用はありません。
しかし、年中毎日のように常用してしまうと副作用が出る恐れも考えられますので、症状が軽い場合にはステロイドが含まれていないMを選んだ方が無難かと思います。
痛みやかゆみを鎮めるリドカインや、炎症を和らげるグリチルレチン酸が痔の症状の緩和を助けます。
傷の治りを助けたり組織の修復を助けるアラトインや、血液循環を助けるタミンE酢酸エステルも含まれています。
楽天⇒ボラギノールA坐薬を確認
楽天⇒ボラギノールM坐薬を確認
プリザSとプリザエースの座薬の特徴や違い
プリザシリーズの座薬にも、Sとエースがラインナップされています。
座薬タイプは、肛門の内側へ作用するので、内側の症状がつらい場合に最適で、薬剤を確実に患部に送り込むことにより高い効果を得られる、ドラッグ・デリバリー・システムの考え方から生まれた静止型座薬です。
ただし、こちらも挿入時の痛みが気になる場合は注入軟膏を選んだ方が無難です。
どちらもヒドロコルチゾン酢酸エステルと言われるステロイドが、軟膏タイプと同じ量だけ配合されています。
違いは、プリザエースのみ塩酸テトラヒドロゾリンが配合されていること。塩酸テトラヒドロゾリンは、出血を抑える働きがあるので、血が出るならプリザエースを選ぶのが最適です。
痛みを抑えるリドカインは1個に60mgが配合されています。
楽天⇒プリザS坐薬を確認
楽天⇒プリザエース坐薬を確認
注入軟膏と座薬の違いは?
軟膏にはチューブタイプと注入タイプの2種類がありますが、このうち注入タイプのものは肛門の内側の痔に効果的です。
座薬も肛門の内側側の痔に効果的なので、注入軟膏と座薬の違いが分かりにくいかもしれませんね。
この違いを一言でいうと、
- 注入軟膏は肛門の内側の痔にも外側の痔にも使えるオールマイティなタイプ
- 座薬は肛門の内側の痔に特化したタイプ
という感じになります。
ですので、
- 肛門の外側だけに痔がある⇒軟膏タイプ
- 肛門の内側だけに痔がある⇒座薬タイプ
- 肛門の外側にも内側にも痔がある⇒注入軟膏タイプ
といった感じでの使い分けがおすすめです。
※どの痔のお薬にも、長期間使用しないでくださいと注意書きがあります。1箱使っても痛みやかゆみが治まらないような場合には、病院で治療するのがベストです。
軟膏・座薬タイプでステロイド配合のものは副作用に注意!
ここまで見てきたように、痔のお薬には大きく分けると
- ステロイド配合
- 非ステロイド
という2種類に分類できます。
痔の市販薬はあくまで症状を抑えるもので、長期常用するものではない
ステロイドは炎症や化膿を抑える効果が期待できますから、一時的な辛い症状にはおススメです。
ですが、長期間常用するものではありません。
市販薬を使う時に説明書をしっかりと読んでいる方は少ないと思いますが、そこには必ずと言ってよいほど「長期間常用しないように」と注意が書かれているはずです。
痔の市販薬は今の症状を抑えることは出来ても、症状が酷くなった痔を完全に治すような効果はあまり期待できません。説明書にも、「痔の症状の緩和」と書かれているだけで「治癒する」という説明は無いはずです。
市販の痔のお薬に配合されているステロイドはあまり強いものではない場合が多いので、痔の症状を緩和するため短期間使用する分には、特に問題ない場合が多いです。
副作用が心配なのは長期使用をした場合
ただし、使用が常用化している場合は注意が必要です。
悪化した痔の痛みやかゆみをなんとかしようと、お薬を年中常用し続けたような場合には、副作用が心配されます。
例えば長期間ステロイドを使い続けると、毛細血管が拡張し、皮膚が赤くなったり薄くなって破けやすくなります。
重症になると、薬を止めても症状が改善することはなく、健康な皮膚に戻れなくなってしまうことすら考えられます。
1箱使っても改善しなければ病院に
専門のお医者さんの見解でも、ステロイド配合の痔のお薬は、自分だったら2週間しか続けないと言っています。
もし、1箱使い切っても根本的な症状が改善されない場合は、使用を中止して病院の肛門科を受診することをおススメします。
痔に漢方が効く?内服薬の効果は?
軟膏や座薬などは西洋医学のお薬ですが、痔に効果の期待できる内服薬タイプの漢方薬もあります。
それが乙字湯と呼ばれる漢方薬で、江戸時代の医師が初めて処方したと言われています。
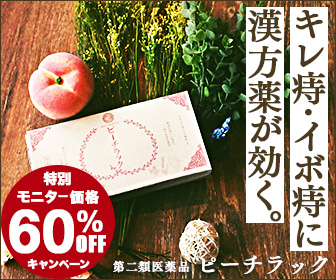
乙字湯【ピーチラック】公式HP
乙字湯が痔に効く理由とメリット
乙字湯は、痔の根本的原因と考えられる便秘や便の硬さを解消することで痔の症状を改善していく漢方です。
ステロイドの副作用がない
1つ目のメリットは、軟膏や座薬のようなお薬と異なり、ステロイドの副作用がありません。
※ただし、漢方薬も医薬品であることに変わりはないため、体質によって下痢などの副作用が起こる可能性はあります。
効果の持続力
効果の持続力も魅力です。
軟膏や座薬はつけている時には痛みやかゆみが鎮まりますが、つけなくなればすぐに症状がぶり返してしまうとう対処療法です。
それに対して漢方薬は、根本原因である冷えや便秘を改善することで肛門が切れにくい状態を作っていきます。
痔の根本原因が冷えや便秘だった場合、その改善によって根本から痔の症状が消えていくので、効果の持続性が高いと言えます。
乙字湯のデメリット
乙字湯のデメリットとしては、効果に即効性は期待できないということが挙げられます。
そもそも漢方薬は長い時間をかけて根本原因を改善していくものなので、痔の痛みやかゆみに対して即効性があるわけではありません。
※ただし、便が柔らかくなるので、排便時の痛みの軽減に関しては即効性があると言えます。
※乙字湯に関しては、こちらの記事で詳細にまとめています。
関連記事⇒痔の飲み薬(漢方)乙字湯の効果と副作用について
痔の薬のおすすめの組み合わせ
ここまで軟膏・座薬・乙字湯(漢方)といった3つの種類の痔の薬について、それぞれの違いや効果・副作用についてまとめてきました。
それを踏まえたうえでおすすめなのが、
- 軟膏・座薬による外側からのケア
- 乙字湯(漢方)による内側からのケア
を並行して行うというやり方。
軟膏や坐薬で対処療法的に症状を鎮め、同時に乙字湯を飲みながら体質改善をしていくという方法です。
両方を使用することで、お互いのメリットデメリットを補い合うことが可能になります。
まとめ
ひとことで痔の薬と言っても、軟膏・注入軟膏・坐薬という3つの形態を持つ外用薬から、漢方を主成分とする内服薬まで、その種類は様々です。
お互いに長所と短所を持っているので、ご自身のニーズに合わせて選択していきましょう。
それぞれ痔に対するアプローチ方法が異なるので、両方同時に使用しても全く問題ありません。






